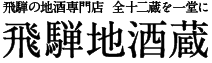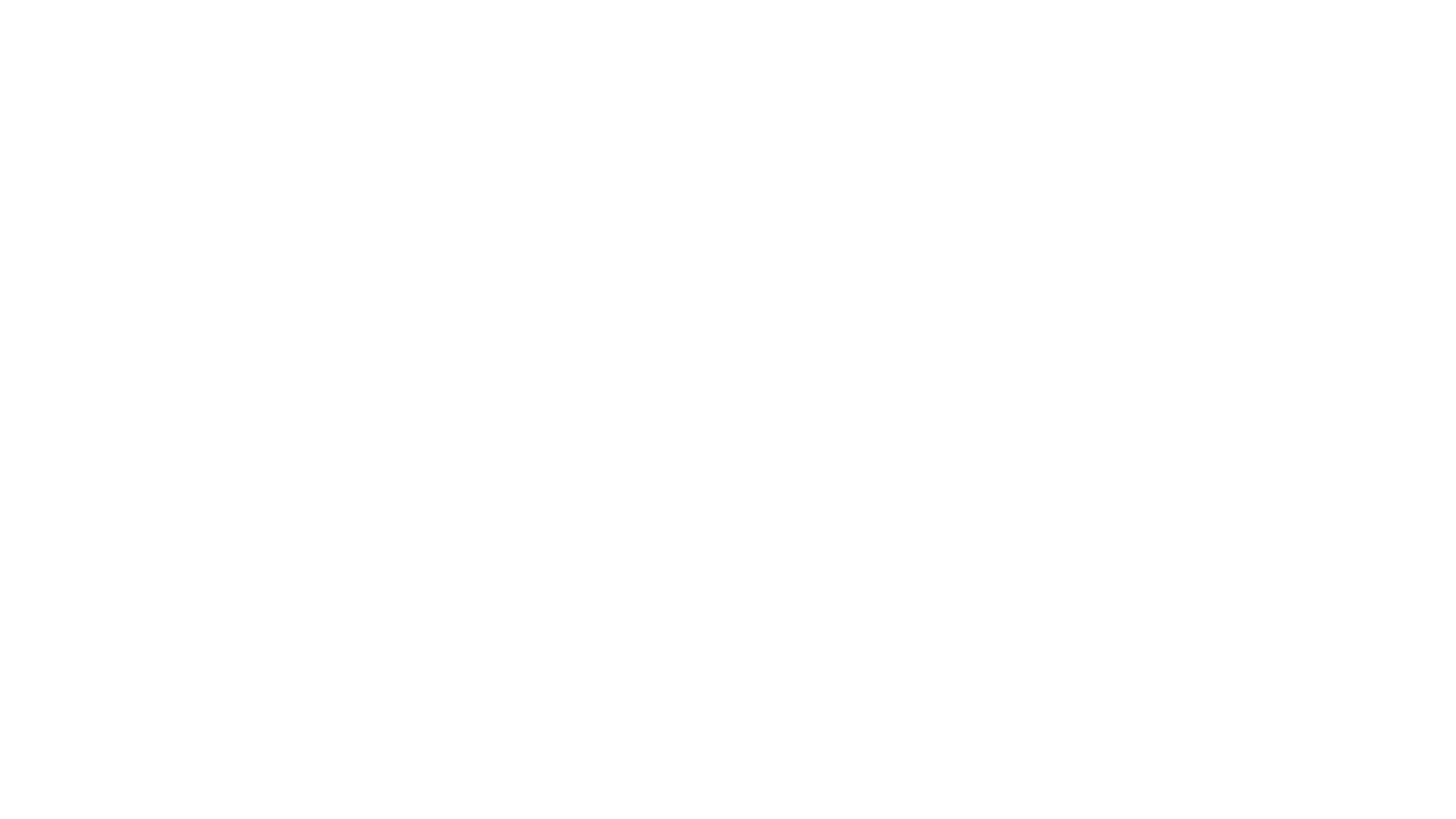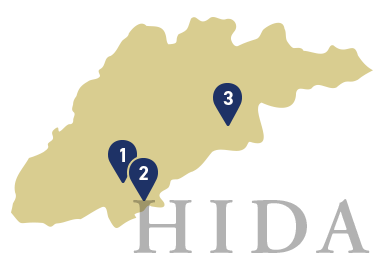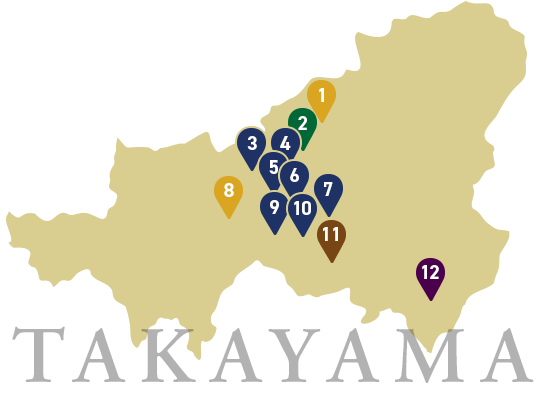蔵元・平瀬酒造は、天神山(藩主金森氏六代107年間の居住跡・現在の城山)のふもと、城下町の一画、海老坂にあります。創業年代は定かではありませんが、菩提寺の過去帳には元和9年(1623)より記録され、約400年、15代続き今日に至っております。
元禄8年(1695)の検地帳には高山一之町村、平瀬屋五郎兵衛とあり、同10年(1697)の造酒屋帳に高山の造酒屋56軒が記載されておりますが、その中に平瀬屋六助の名があります。
天保14年(1843)、造酒屋は約半数の26軒となりましたが、当時の町年寄日記には、酒造米八十八石ニ斗および、平瀬市兵衛の名も書かれ、その日記は現在も高山市郷土資料館に保存されています。
大正元年(1912)、地域火災延焼により仕込蔵・文庫蔵を残し、住宅他酒蔵数棟を全焼しました。また翌年には、12代目当主は疲労のあまり床につき、二週間後に逝くなどの、相次ぐ不幸に一時はどうなることかと心配しましたが、主従一丸となり苦難を乗り越え、再興に至っております。
大正4年(1915)頃、灘では清酒という新しい酒ができて大変好評との話しを聞き、辰馬酒造に見学し、丹波より杜氏を招聘して飛騨で初めて清酒を造りました。その清酒を『灘流正宗』と銘々し発売しましたところ、非常に好評で、次第に製造量を増やし現在の基礎を造りました。
第二次大戦後、財産税、富裕税、農地解放と矢継ぎ早に新政策が施行される等の大打撃を受けた中で、何とか危機を乗り越え、14代目当主が、工場の改築・設備の近代化を行い、家業(酒造業)の発展のため努力しました。
いつの頃からか、平瀬家では代々平瀬市兵衛を襲名し、『他の商売には如何なることがあっても振り向かない。酒造り業一筋に生きる。』を家訓とし、今も固く守り継がれております。